教員
マルクスの眼差しで、現代の世界を読み解く。
的場 昭弘
経済学部 社会・経済思想史専攻
専門分野:マルクス研究
私たちは、資本主義の時代を生きている。
その本質をはじめて徹底的に分析したのは、19世紀を生き、20世紀に多大なる影響を与えた知の巨人、思想家のカール・マルクス(1818 - 1883)だ。
的場昭弘はほぼ半世紀に及び、マルクスと向き合い続けてきた。
INDEX
01商品の価値の源

ピカソが描いた「アルジェの女たち バージョン0」、1億7,936万5,000ドル(約215億円)。ジャコメッティの彫刻「指さす人」、1億4,128万5,000ドル(およそ170億円)―。今年の5月11日に行なわれた、アメリカの美術品オークション大手クリスティーズでの落札価格だ。破格の値段はメディアで驚きをもって報じられ、報道によれば、これらは美術品の競売史上の最高額記録を塗り替えたという。
かたや、この社会にはさまざまな商品が存在し、同じ商品の価格が、時と場合に応じて変わることがある。たとえば、定価1,800円で買った本を古本屋に売りに行くと二束三文にしかならず、それが古本屋の書棚に並ぶと100円で売られていたりする。
価格は需要と供給のバランスで決まる。それが現代の常識だ。学校でもそう教わる。だが、価格はそれだけで決まるものではないと的場は指摘する。
「商品には、価格を支える本質的な “価値”があります。商品をつくるのにどれだけの労働が必要か。それが商品の価値を決めるとマルクスは考えました」
需給のバランスもたしかに価格に影響を与えるが、その根底には人間の営みとしての労働がある。「労働価値説」と呼ばれるこの考えは、マルクスの議論の出発点となっている。
02資本主義とは何か
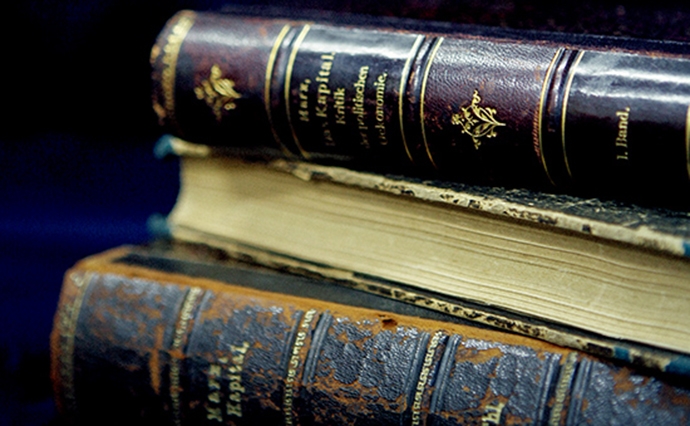
価格と価値―。似ているようで両者は異なる。的場は、「マルクスにとっつきにくさを感じるのは、普段何気なく暮らしていると見過ごしがちなことを問題として扱うから」と前置きし、両者の関係を次のように述べる。
「マルクス晩年の1870年代、“限界効用” と呼ばれる経済理論が広まりました。商品の本質的な価値を問うのをやめ、買い手の主観的な満足(効用)を価値ととらえ、支払い額の単位あたりの効用が最大になるように、買い手は購買行動を決めているという理論です。それに従えば、ピカソの絵に大金を払うのは、その人がそれに見合う効用を感じているからということになります」
この学説は、価値が主観的なものであるとの主張から「主観価値学説」とも呼ばれる。価値とは何かという厄介な問題を脇に置き、シンプルな見解は広く受け入れられることになった。だがそれにより、資本主義の本質をつかみづらくなったと的場は批判する。
「資本主義とは、資本の絶えざる自己増殖のことです。資本を投下して利潤を上げ、それを再投資して利潤を拡大し資本を増やす。この運動が資本主義の本質です。問題は、価値の背後に労働があることを切り捨てると、利潤が生まれる仕組みをうまく説明できないことです。安く買って高く売ればいいじゃないかと思うかもしれませんが、みながそれをやろうとすると、誰も商品をつくる人がいなくなって、経済活動は破綻します」
マルクスは、利潤のことを「剰余価値」と呼ぶ。この語が示すように、利潤とは労働から生まれた価値の一部だ。労働から生まれた価値は、本来なら労働者の取り分であるはずが、資本家が労働者にすべてを渡すことはない。一部を「ピンはね」し、残りを給料として労働者に支払う。その「ピンはね」した価値こそが利潤(剰余価値)だ。
03資本主義の終わりの始まり
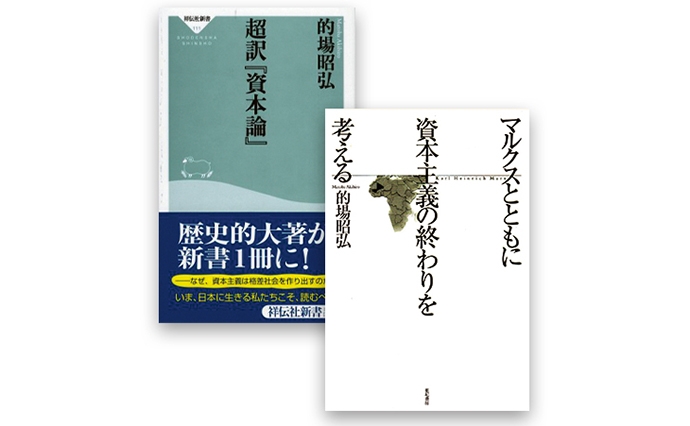
マルクスは『資本論』で、資本主義の徹底した分析を行った。労働と価値の関係や利潤が生まれるカラクリの解明のほか、資本主義が抱える本質的な矛盾も明らかにした。それこそがマルクスの真髄だ。
「その矛盾のひとつは、“利潤率の傾向的低落の法則” として知られます。“利潤率” とは、投下資本に対する上がりの利潤の割合のこと。資本主義は成長の果てに、読んで字のごとく利潤率が低落する傾向にあり、資本の増殖にブレーキがかかる宿命を負っています」と的場は語る。資本主義の成長は、資本主義自体の終わりへ向かう歩みに等しいというわけだ。
この法則がなぜ成り立つかを、限られた紙幅で噛み砕くのは難しい。だが、マルクスの指摘はすでに現実のものとなりつつある。日本銀行が長年推し進める「ゼロ金利政策」がその象徴だ。金融資本の利子は、商品をつくって売る産業資本の利潤を源泉とする。金利すなわち利子率をゼロに近づけなければならないのは、社会全体で見て利潤を上げづらくなっていることが背景にある。昨年来、エコノミストの水野和夫氏(日本大学教授)が著書の『資本主義の終焉と歴史の危機』(集英社新書)で主張し、注目を集める論調だ。
資本主義が終わりつつあるとして、その後にどんな社会が訪れるのか。それは誰にもわかりようがない。共産主義に可能性を感じていたマルクスとて、未来を予見することは慎重に避けていた。「未来予測はその時代の制約を受けると、十分すぎるほど分かっていたからではないか」と的場はその理由を推測する。「これからどうするかは、現代を生きる人間が考えていかなければならない」と、的場は言葉を添える。
04マルクスと歩んだ半世紀
的場のマルクスとの出会いは、ほぼ半世紀前の1967年、的場が中学3年生のころに遡る。
「その年は『資本論』刊行からちょうど100年。それを記念して刊行された『資本論』の解説書を書店でたまたま手にしたのがマルクスとの付き合いの始まりです」と当時を懐かしそうに振り返る。
高校受験に失敗し、挫折を味わった的場にとって、マルクスの言葉が支えになった。「受動的な苦しみも、人間的に言えば、人間のひとつの自己の享受の仕方だ」(『経済学・哲学草稿』)そして、「マルクスを研究するために」大学に進学して今日に至る。
多感な10代半ばからマルクス一筋を続けているうち、「マルクスが母国語のように」なってきたと的場は言う。「マルクスのものの見方は独特で難しいと言われますが、私からするとマルクスのものの見方が基本にあるので、別の見方ができることの方が不思議に思えます」とのこと。もちろん、マルクスを外から客観的に見るために、現代の社会情勢をはじめ、さまざまな分野の研究も怠らない。
「いずれはマルクスの伝記を書きたい」と語る的場は、意外な素顔について教えてくれた。マルクスは資本主義社会を批判するため定職に就かず、在野の研究者として困窮のさなか『資本論』を書き上げたと言われるが、それは旧ソビエト連邦がマルクスを美化するためにこしらえたつくり話なのだという。
「マルクスも彼の妻も裕福な家庭で育ち、盟友エンゲルスも成功した資本家です。エンゲルスにお金の無心をする手紙が残っていますが、それは湯水のようにお金を使うから。マルクスが手にしていた収入は、ほとんど上流階級と言えるほどです」マルクス一筋半世紀―。言葉にするのはたやすいが、何が的場の心をそれほどまでにとらえ続けるのか。
「マルクスは古典的教養豊かな博覧強記の人で、読み解くのは簡単なことではありませんが、いつ、どんなふうに読んでも知的刺激を得られます。それがマルクスの大きな魅力です。マルクスをどう解釈するとかマルクス主義をどう活かすとか、それも大事なことですが、私が解き明かしたいのは、マルクスの思想を産み出した彼自身の人物像です」
掘れども尽きない知の鉱脈。その偉大なる山と、的場は今日も対峙する。
※内容はすべて取材当時のものです。


