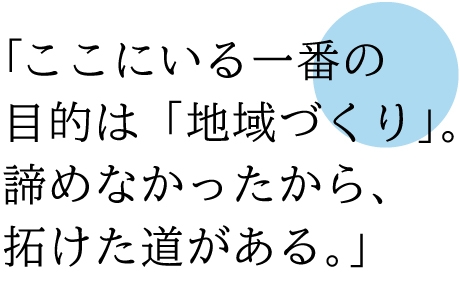卒業生
鈴木 寛太
数ある大学生活の思い出の中で、人生を変えたのが東日本大震災の被災地支援活動「KUボランティア駅伝」です。この活動を通して岩手が大好きになり、ついには移住を決意。ぶどうづくりに、地域づくりに、汗を流す毎日。人生は小説よりも奇なり!
かんたはうす運営組合 副組合長
(2014年卒業)
INDEX
01噴水前で号泣…からの大逆転。数ある思い出の中で、人生を変えた「震災ボランティア」。
入学してすぐに参加する初年度ゼミの担当が浅海典子先生で、3年次でも浅海ゼミに入り、ゼミ長を務めました。経営学部では毎年「インターゼミナール大会」という、ゼミ対抗のプレゼン大会を実施しています。毎年白熱するプログラムで、絶対に参加しよう!と決めていて、仲間と一緒にテレワークをテーマに挑みました。本番発表が間近に迫った大会3日前、まさかの内部分裂が起きました…。平塚組の皆さんならご存知かと思うのですが、キャンパスの噴水の前で「なんで、みんなまとまってくれないんだ」と号泣(笑)。なんとかチームを立て直し、本番は全力で臨みました。結果発表の時間になり次々と賞が決まっていきます。もう呼ばれることはないと思った、最後の最優秀賞の発表で、僕らのチーム名が呼ばれた時の感動は今でもはっきりと覚えています。この大会の他にも、サークル活動やオープンキャンパススタッフと、たくさんの思い出が詰まった大学生活でしたが、中でも、僕の人生を変えたのが「KU東北ボランティア駅伝」への参加でした。

2011年4月に発足した「KU東北ボランティア駅伝」は、東日本大震災の被災地支援活動として立ち上げられました。日本で起きた未曾有の出来事を自分の目で確かめたい、何か力になりたい、そんな気持ちに突き動かされて、2011年9月、大学2年の時に初めてボランティアに参加しました。合計で7回ほど訪問しましたが、回を重ねるごとに岩手の人の明るさや優しさに触れて、ここで生活したいと思うようになりました。岩手に惹かれながらも、就活の時期を迎え、一度は神奈川の企業に就職しました。でも、岩手と離れるほどに心のモヤモヤは大きくなり、一度切りの人生なら行くしかないと会社を退職し、岩手行きを決めました。
インターゼミナール大会で最優秀賞を受賞。仲間と記念撮影
02300坪からスタートした「ぶどう物語」。みるみる広がっていった人の輪。

岩手に行くことを決めたきっかけは、花巻市で「地域おこし協力隊」という期間限定の移住者を募集していて、運良く協力隊に参加することが決まりました。友達も知り合いもいない土地でしたが、それ以上にワクワク感が大きかったです。
KU東北ボランティア駅伝にて、サンタさんに扮して子ども達にプレゼントを渡すボランティアをしている様子

勤務地となった大迫町は70年以上前からぶどう栽培が盛んな地域なのですが、高齢化が深刻で、ぶどう農家や地域を盛り上げることが僕たちの任務でした。東京などから友達を呼び、ぶどう農家さんのお手伝いをしたり、イベントを行ったり、ワイワイと過ごした3年間でした。任期終了が迫ったある日、仲の良い農家さんから、300坪のぶどう畑を誰かに預けたいという話が持ちかけられたのです。借り手を探したのですが一向に見つかりません。「自分でぶどうを作ったらどうなるんだろう…?」そんな気持ちが湧いてきて、最終的に自ら名乗りをあげました。協力隊を退任し、2017年5月、大迫町で僕のぶどう農家としての物語が始まりました。同じ年に、活動拠点となる「かんたはうす運営組合」を設立しました。かんたはうすの運営には、元大迫総合支所の支所長で、現かんたはうす運営組合の組合長、役場の元上司の方、そして栽培の最盛期に手伝いに来てくれる西和賀町の仲間たち、大迫高校の生徒たち、みんなの協力が欠かせません。

300坪からスタートしたぶどう畑は現在、その10倍の3,000坪にまで広がっています。野球場がまるまるひとつ入るような広大な土地を、仲間に助けられながら栽培しています。
今、畑で作っている品種はキャンベルを筆頭に、シャインマスカット、サニールージュなど生食用が8種類。ロースラーというワイン用のぶどうも手掛けているのですが、この品種は60年ほど前に大迫町と友好都市提携をしているオーストリアのベルンドルフ市から苗木を分けてもらった経緯があり、町から持ち出すことができない大変貴重な品種です。このロースラー100%を使って「KANTA WINE」も作っています。ぶどう畑の仕事は朝4時起きですし、肉体を酷使します。辛いんです(笑)。でも、仲間とやりがいがあるから頑張れています。僕の作ったぶどうをおいしいねって目の前で食べてくれる。記念日に僕のワインを飲んでくれるなんて、究極のやりがいです。この喜びは決してお金で買うことはできません。
最近は、ぶどう栽培以外の活動も忙しく、そのひとつが大迫魅力化コーディネーター。これは、過疎化が進む大迫町唯一の高校をどう存続させていくのか、高校生や先生と一緒に考えるものです。町の魅力づくりの一環として、まずは町内の古いベンチのリメイクに取り組みました。高校生がアイデアを出し自分たちで彩色したぶどう柄の可愛いベンチは、地方紙に取り上げられ、地域の新しい魅力になっています。また、大迫小学校にある「めげな会」という住民団体の会長も務めています。校庭のぶどうのお世話を、小学生と高校生が一緒に行う仕組みを作り、世代を超えた交流が生まれました。今年、花巻市で最年少の公民館長になり、それを聞きつけた沿岸の方から連絡を受け、大船渡市で講演会をすることも決まりました。
03活動を続けていくことが、温かく僕を迎え入れてくれた東北への恩返し。
地域おこし協力隊の頃から変わらない思いが、「外からの関わりを増やして、地域を元気にすること」です。人が関わり続けられる町って、どんな町なんだろうとずっと考えてきました。東京から大迫に来た人が「また来年くるね」と言えば、東京の方を迎えた大迫の人も「また来ないかな?」と思う、作りたいのはそんな気持ちの通いあった関係性です。
その関係性って何だろうと考えてみたら、大学時代にボランティア駅伝で感じた気持ちそのものなのだと気づきました。岩手の人たちに「かんちゃん、来ないの?」と言われると、僕はそれが心地よくて、すぐにでも出掛けたくなりました。ボランティアに参加していなければ、この気持ちは分からなかったし、今の自分はなかったと思います。震災が起こって、辛いことがたくさんあって、それでも東北の人は前を向いて進んでいます。まだまだ復興は道半ばですが、その中で明るく受け入れてくれた方たちは、僕たちに思いを寄せてくれていた。その気持ちを当事者となって知ることができ、改めてこの町を元気にしたいと思うし、ここで活動を続けていくことが、東北への恩返しになるんじゃないかと思っています。
花巻生まれの宮沢賢治は、雨ニモマケズ、風ニモマケズと言いました。でも、鈴木寛太は、負けてもいいんじゃない?と思うんです(笑)。ただ、負けてもいいから、諦めないでほしい。僕は諦めなかったから、東北に行き続けることができたし、たくさんのつながりができました。やり続けることにこそ、大きな意味があると思っています。
※内容はすべて取材当時のものです。