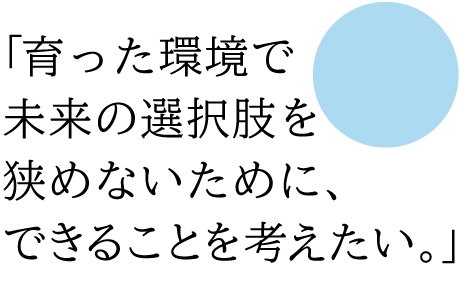卒業生
二挺木 真菜
高校生の頃に行った予備校で、私は偶然、大学という選択肢を手にいれました。その一言があったから経営学部に進学し、想像もしていなかった未来にいます。自分の経験を通して、次の世代を担う子どもたちのために、私ができることを考えたい。
積水ハウス株式会社 神奈川中央支店 営業
(2017年卒業)
INDEX
01大学進学という道を開いた、予備校での思わぬ助言。
母はとても厳しい人で、よく言われていたのが「ナンバーワンになれない人は、オンリーワンにもなれない」という言葉。勉強でもスポーツでも、例え文化祭の配役であっても「何でも一番を取りなさい、みんなに良くしなさい」と教えられて育ちました。その教えを守って曲がらずに良かったこともありますが、娘を思うがあまり、かなり厳しい母親だったので(笑)、時には不満をパワーに変えて頑張るような中学・高校時代を過ごしていました。
高校卒業後はブライダルプランナーになる夢を叶えるために、専門学校への進学を考えていました。お金に余裕がある家ではなかったので、大学進学なんて全く頭になかったんです。ある日、予備校の無料夏期講習に参加したのですが、その時の塾長面談でブライダルの専門学校を志望していることを伝えると、ブライダル業界に進むにしても、大学に進学した方が自分の就きたいポジションにつける可能性があるからと、大学進学を後押ししてくれました。それまで私の周りに大学受験を助言してくれる人は誰もおらず、その時初めて「大学という道もあるのか」と背中を押していただいたことが進学のきっかけになりました。
02やることに意味のないものなんてない。人脈と経験は自分を助けてくれる。

入学後は、とにかくいろいろな経験をしたいと考えていました。大学2年の時には、海外インターンシップ制度を利用し、1ヶ月半シンガポールで過ごしました。現地の配属先は“石材店”と聞かされていたのですが、実はチャンギ空港のフロアタイルをデザインするような大きな会社で、そこで建築の仕事に魅了されました。英語はとても苦手でしたが、何とか気持ちと根性で乗り切って(笑)。実はこの時が初めての海外で、初めてのインターンシップ、さらに渡航は両親にも相談せず独断で決定。初めて尽くしの経験が、自分を大きく成長させるターニングポイントになりました。
経営学部にはさまざまな体験型の学びがあり、ゼミ生3人で「ビジネスプランコンテスト」に参加しました。これは、新規事業を考えてプレゼンテーションするもので、審査員は経営学部の先生やプロの銀行マンの方々。収支計画の提出など、実際にビジネスとして成立するかもシビアに見られます。私たちが提案したのは「ハラール(※)フードビジネス」というもので、当時の訪日外国人は、アジア圏でかつイスラム教を信仰している方が多いことを知り、着眼した企画でした。テーマがギリギリまで決まらなかったので、最優秀賞をいただいた時には嬉しさと驚きでいっぱいでした。
(※)ハラールとは、イスラム教の信者の方が食べられる食品のこと
ホストファミリーとの写真(着いてすぐにトリプルルックを用意されるくらいに温かいファミリーでした)

大学3年の頃には相模原の観光親善大使にも選ばれ、大学生活とは別に相模原市のPR活動にも取り組みました。イベントに参加したり、メディアに出たりと、さまざまな活動を通して自分の育った街を再認識することができました。
また学生時代に頑張ったのは学費のためのアルバイト。大学1年の前期分を両親に出してもらった後は、卒業までアルバイト代で学費を捻出しました。神奈川大学には成績優秀者に対する奨学金があり、その可能性もあったので学力の維持にも努めました。
勉強でも、遊びでも、課外活動でも、大学時代は何でも真剣にやることが大事だと感じます。やることに意味のないものなんて、ひとつもありません。自分が経験したことが何かに生きるかも知れないし、誰かとつながるかも知れない。人脈と経験はいつか自分を助けてくれるはず。だから、いろんな経験をして、いろんな人に出会ってほしいと思います。
03今、関心があるのが「子どもの貧困と学習」。自分にできることを模索していきたい。
現在は、積水ハウスの戸建営業を担当しています。海外インターンシップで建築分野に興味を持ち、就職先としてゼネコンなども考えましたが、企業を相手にするよりも、接客が好きな自分には対個人の方が向いていること、また事務職ではなく現場の最前線に立ちたい思いがあり、住宅メーカーの営業職に就職を決めました。
仕事で意識していることは「違和感」。コミュニケーションに違和感があるということは、相手が何かに納得していないことの表れだと思いますし、私の意図とは違う解釈をされているのかも知れない。違和感を感じる時には、気持ちをきちんと伝えるために、言葉を尽くすようにしています。もうひとつ大切にしているのは、良い意味で、お客様をお客様と思わないこと。お客様と思った瞬間に相手が見えなくなってしまうので、年が近い方は友人、年が離れた方は親戚のような気持ちで接しています。相手が私の友人なら、親戚なら、どういう風にしてあげたいか、どうしたらわかってもらえるのかを考えると、相手の気持ちが見えやすくなります。多くのお客様に「メーカーではなく、二挺木さんだから建てたんです」と言葉を掛けてもらえることが最高の喜びです。

大学時代、ゼミの担当だった湯川先生に「誰のために、何のために」を学びました。そもそもは「誰のために何のために、を解決することがビジネスだ」と授業で学んだのですが、仕事にも大いに通じるものがあります。「誰のために、何のために」を考えることは本質的にお客様のためなり、お互いに違和感なく進めることができ、ストレスのない契約になる、だから契約後も問題が起きない。この学びは働く私の指針にもなっています。
高校生の頃に行った予備校で、私は偶然、大学という選択肢を手にいれました。その一言のおかげで神奈川大学経営学部に進学し、想像もしていなかった未来にいます。そういう経験があったからこそ、次の世代を担う子どもたちにも同じようにしてあげたい。もし、経済的な理由で大学進学を諦めようとしている子がいるなら、奨学金を借りてでも大学に進学することを助言すると思いますし、子どもが生まれた環境や貧困で学習の差があってはならないと強く思います。仕事とは別の次元で将来、子どもの貧困と学習に関することに携わりたい気持ちもあり、自分に何ができるのか模索していきたいです。
※内容はすべて取材当時のものです。